この記事では、ガス給湯器の水抜き方法と凍結防止対策を、初心者でも迷わず実践できるように解説します。まず、最初に準備すべき道具や安全確認の手順を整理し、基本的な水抜きの流れを紹介します。次に、一戸建てとマンション・アパートなど住宅タイプ別のやり方を詳しく解説。主要メーカー(ノーリツ・リンナイなど)の注意点や、電源・ガスの扱い方、再給水と試運転のコツもカバーしています。さらに、水が抜けない・お湯が出ないなどのトラブル解決策や、業者依頼が必要なケースの判断基準、費用相場まで幅広く網羅。最後に、実例・FAQも掲載し、すぐに実践できる構成にまとめました。
- はじめに
1-1. 結論
結論から言うと、ガス給湯器を凍結から守るためには、気温が氷点下になる前に水抜き作業を行うことが最も重要です。
特に冬場の寒波や夜間の冷え込みが予想される前に、ドレン栓や水抜き栓を開けて残水をしっかり排出しておくことで、給湯配管や追いだき配管の凍結・破裂トラブルを防止できます。
この事前の凍結対策を行うだけで、給湯器本体や配管の破損を未然に防ぎ、修理費用の発生リスクも大幅に減らせます。
1-2. 対象読者
この記事は、一戸建て・マンションなどあらゆる住宅タイプの方を対象としています。
特に、冬季に不在期間がある人や、初めて水抜きを行う初心者にも分かりやすい内容です。
専門知識がなくても手順を追えば安全に実施できるよう構成しています。
1-3. なぜ水抜きが必要か
水抜きを怠ると、給湯器内部や給湯配管内の水が凍結して膨張し、配管破裂や本体損傷、さらにはガス漏れ事故につながる危険性があります。
特に屋外設置型や寒冷地のガス給湯器は、氷点下の冷え込みや寒波の影響を受けやすく、凍結トラブルのリスクが高い傾向です。
一度凍結して破裂すると、修理費用は数万円〜十数万円に及ぶこともあり、場合によっては本体交換が必要になるケースもあります。
そのため、事前に水抜き栓やドレン栓を開けて残水をしっかり排出し、防寒カバーや凍結防止ヒーターを併用することが効果的です。
このような予防メンテナンスを行うだけで、凍結防止と修理コストの削減を同時に実現できます。
したがって、気温が氷点下に下がる前に準備と水抜きを済ませることが、冬の安全で快適な暮らしを守る第一歩です。
- 水抜きの前に準備するものと安全確認
2-1. 必要な道具一覧
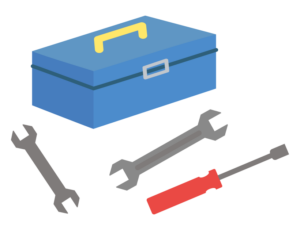
水抜き作業を始める前に、必要な道具と安全対策の準備を整えておきましょう。
以下の工具や備品をそろえることで、凍結防止作業をスムーズかつ安全に進められます。
- バケツまたは洗面器(排水や残水を受ける用)
- モンキーレンチ(止水栓やドレン栓を回す際に使用)
- タオルや雑巾(水漏れ・飛び散り防止)
- 手袋または防寒手袋(冬季の冷たさや手元の安全対策)
- 取扱説明書(メーカーごとの水抜き栓や排水位置を確認)
特にモンキーレンチはナットサイズに合ったものを使用し、無理に回さないよう注意が必要です。
サイズが合わない工具を使うと、配管接続部や給水バルブの破損につながることがあります。
また、作業前に電源を切り、ガス栓を閉じるなどの安全確認も忘れずに行いましょう。
これらを事前に整えておくことで、作業中の水漏れやトラブルを未然に防止し、凍結予防対策をより確実に実施できます。
2-2. 作業前の安全確認

次に、水抜き作業を始める前の安全確認を行いましょう。
まず、給湯器本体の主電源スイッチをOFFにし、リモコンの運転を停止します。
続いて、ガス元栓をしっかり閉め、燃焼部に炎が残っていないか確認してください。
このとき、都市ガス・プロパンガスいずれの場合も、ガス漏れの有無を必ずチェックすることが重要です。
また、屋外設置型の給湯器で作業する場合は、足元の凍結や滑りやすい箇所に十分注意しましょう。
雪や氷が残っている場所では転倒の危険があるため、滑り止めマットや防寒手袋を用意すると安心です。
このように、電源・ガス・作業環境の3点を事前に確認してから始めることで、感電やガス漏れ、転倒といった二次災害を未然に防止できます。
安全を確保してから作業を行うことが、凍結防止対策を確実に進めるための第一ステップです。
2-3. 注意すべき健康・安全上のポイント
高齢者や小さなお子さまがいる家庭では、給湯器の水抜き作業を一人で無理に行わないことが大切です。
事前に家族へ声をかけ、家庭内で安全確認を共有してから作業を始めましょう。
給湯器周辺は水漏れや湿気が多く、足元が滑りやすい環境です。誤って転倒するとケガにつながるおそれがあるため、転倒防止マットやタオルで足場を整えるなどの安全対策をしておくと安心です。
また、作業中に小さなパッキンやナットなどの部品が外れる場合もあります。誤って子どもが触れたり飲み込んだりしないよう、子どもの安全確保と注意喚起も忘れずに行いましょう。
安全を最優先にしたうえで、焦らず正しい手順と確認ポイントを押さえれば、失敗なく水抜きを完了できます。
結論として、「準備 → 確認 → 安全確保」の3ステップを守ることが、給湯器の水抜き作業を安全に成功させる鍵です。
- 基本の水抜き手順
3-1. 手順の全体像
結論から言うと、給湯器の水抜き作業は3ステップで完結します。
正しい手順を守ることで、凍結や故障を防ぎ、安全に冬を越すことが可能です。
基本の流れは以下の通りです。
- 給湯器の電源・ガスを止める(感電やガス漏れ防止のため)
- 給水・給湯の元栓を閉じる(配管内に新たな水を入れない)
- 排水ドレンバルブを開けて水を抜く(内部の残水をしっかり排出)
この3ステップを守るだけで、一般的な凍結防止の水抜き作業は完了します。
ただし、屋外設置型やマンションのベランダ設置タイプなどでは構造が異なるため、
必ずメーカーの取扱説明書や設置環境ごとの操作部を確認してから行いましょう。
安全確認と正しい手順を意識すれば、トラブルや誤操作を防ぎ、
給湯器の寿命を延ばすメンテナンス効果も期待できます。
3-2. 元栓と止水栓の見つけ方・操作方法

給湯器の元栓と止水栓を正しく閉めることは、凍結や水漏れを防ぐ基本の防寒対策です。
元栓は多くの場合、屋外のガス配管やメーターボックス内にあり、レバーを横向きにすると閉栓できます。
また、止水栓は給湯器本体の下部にある「給水・給湯」ナットをゆっくり回して閉めましょう。
手で回らない場合はモンキーレンチを使用しますが、力を入れすぎると配管破損やガス漏れの恐れがあります。
正しい手順を守れば、修理費用や凍結トラブルを未然に防ぎ、安全な水抜き作業が可能です。
3-3. 給湯器本体のドレン(排水)から水を抜く方法
止水栓を閉じたら、給湯器下部のドレンキャップ(排水ドレン口)を緩めて排水します。
バケツを下に置き、内部の水を完全に抜くことが凍結防止のポイントです。
ドレン口が複数ある場合は、順番に開けて全ての系統を排水しましょう。
排水後はキャップを確実に閉め直し、水漏れや破損を防止します。
特に屋外設置型の給湯器は残水が凍結しやすいため、完全排水の確認が重要です。
3-4. 配管の残水を抜くコツと確認方法
最後に、給湯器から室内へ伸びる配管内の残水を抜きましょう。
台所や洗面所などの蛇口を「開」にして空気を入れると、給湯配管の水が押し出されて確実に排水できます。
排水後は蛇口を閉め、ドレンキャップを戻して凍結防止を確認してください。
この手順を守れば、初心者でも安全に給湯器の水抜きが完了します。
- 住宅別のやり方
4-1. 戸建ての給湯器での具体手順

戸建て住宅での給湯器の水抜きは、次の手順を守ると安全です。
まず屋外の水道元栓を閉め、続いて給湯器本体の水抜き栓を開けます。最後に室内の蛇口をお湯側にして空気抜きを行えば、配管内の残水をしっかり排出できます。
特に屋外設置の給湯器は、配管やタンク内の水が凍結して膨張・破損するリスクが高いため、冬前の凍結防止としてこの手順が重要です。
具体的には、
- 外の給湯器を確認し、**給水バルブ(青)と給湯バルブ(赤)**を特定する。
- 給水バルブを閉め、下部にある**水抜き栓(銀色や樹脂製キャップ)**をゆっくり緩める。
- キッチン・浴室・洗面の蛇口を「お湯側」に回し、空気が通るようにする。
この3ステップを順に行うことで、内部の残水を完全に抜き取り、凍結や配管破損を防止できます。
4-2. 屋外配管・凍結しやすい箇所の対策
屋外にある給湯器の配管は、「保温材+防寒テープ」で二重に覆うことが凍結防止の基本です。
露出している水道管や給湯管は、外気温の影響を受けやすく、冷え込みによる凍結や膨張・破裂のリスクが高まります。
対策として、ホームセンターで手に入る発泡ゴム製の保温チューブや断熱材を配管にしっかり巻きつけ、接合部やエルボ部分は防寒テープで隙間なく密閉しましょう。
とくに地面近くや蛇口まわりの配管は凍りやすいため、重点的に保温するのが効果的です。
このように、保温材と防寒テープを組み合わせた凍結対策を行えば、配管温度を0℃以下に下げず、破裂や水漏れのトラブルを未然に防ぐことができます。
4-3. 土間・外置きユニットの排水注意点
外置きタイプのガス給湯器は、水抜き前に排水経路の確認と清掃を行うことが基本です。
屋外設置の給湯器では、排水口やドレン排水の詰まりがあると、水がうまく流れずに凍結し、逆流や圧力不良、配管破損を招く恐れがあります。
まず、給湯器下部やコンクリート土間にある排水口をブラシなどで清掃し、ゴミや氷を取り除きましょう。
排水の傾斜が足りない場合は、プラスチックトレーなどで水を誘導すると安全です。
このように水はけの確保と凍結防止対策を同時に行えば、屋外配管や本体への負担を減らし、冬場でも安心して給湯器を使用できます。
定期的な冬季メンテナンスとして実践することが、トラブル防止の近道です。
- 住宅別のやり方:マンション・アパート

5-1. 共用配管と個別配管の違い
マンションやアパートなどの集合住宅では、室内給湯器から先の専有部分のみを自分で水抜きするのが基本です。
共用部の配管や元栓は建物全体の給水系統につながっており、個人判断で操作すると断水トラブルや水漏れ事故につながるおそれがあります。
具体的には、共用廊下にあるパイプスペース(PS)内の配管は共用部分です。
給湯器がバルコニー設置型の場合は、室内側の蛇口(キッチン・浴室・洗面所)を開けて残水を抜くだけで十分です。
共用配管や元栓操作は、必ず管理会社や管理組合へ事前に連絡し、対応を任せましょう。
個人でできる範囲を守ることが、凍結防止対策とトラブル防止のどちらにもつながります。
5-2. 管理会社・管理組合への確認ポイント

水抜き作業を行う前に、必ず管理会社や管理組合へ「共用配管の扱いや復旧手順」を確認しましょう。
給水バルブや止水栓を閉めると、共用部分の給水管にも影響し、他の住戸で断水トラブルが起きる場合があります。
その結果、管理規約違反や責任問題に発展するケースも少なくありません。
特にマンションでは、
- 「凍結防止作業をしたいが、元栓を閉めても大丈夫か」
- 「指定業者による対応が必要か」
といった点を事前に確認することが大切です。
マンションによっては、共用設備の操作や配管の取り扱いに関して、管理会社の承認が必要な場合もあります。
手順を守らずに作業を進めると、漏水事故や設備故障、損害賠償のトラブルにつながるおそれがあります。
このように、管理規約と確認手順を徹底することで、凍結対策や水抜き作業を安全に行い、トラブルを未然に防ぐことができます。
5-3. 室内設置給湯器の場合の手順と注意点
室内設置型の給湯器は、水抜き栓がないタイプが多く、蛇口操作で空気を抜く方式が主流です。
これは、防音・防寒構造により、内部配管の水抜きが限定的になっているためです。
実際の手順は次の通りです。
- **給水元栓(止水栓)**を閉める
- 全蛇口をお湯側にして5〜10秒開放し、圧力と空気を抜く
- エラー表示が出た場合は、リセット操作で解消
室内タイプの水抜きは、「水を完全に抜く」より「内部の圧力を抜く」イメージで実践すると安全です。
- メーカー別のポイント
6-1. ノーリツ(Noritz)の注意点
ノーリツ製の給湯器では、特においだき配管の水抜き忘れに注意が必要です。
フルオート機能搭載機種では、追いだき管や浴槽まわりの循環口にも水が残る構造になっているためです。
安全な水抜き手順は次の通りです:
- **リモコン操作で「追いだき配管洗浄モード」**を実行
- 浴槽の循環口を外して全体排水
浴槽まわりも含めた全体排水を徹底することで、漏水や凍結リスク、故障を防ぐことができます。
6-2. リンナイ(Rinnai)の注意点
リンナイ製の給湯器では、凍結防止ヒーターが自動で作動するため、本体電源は常に通電状態を維持することが重要です。
電源を切るとヒーターが停止し、夜間の冷え込みや外気温0℃以下の寒冷期に配管凍結のリスクが高まります。
安全に使用するためのポイントは次の通りです:
- リモコン電源を切っても、本体電源は入れたままにする
- コンセントを抜かずに「運転停止」状態にしておく
凍結防止機能を最大限に活かすには、通電状態の維持が不可欠です。
6-3. その他メーカーの一般的留意点
メーカーが異なる給湯器でも、水抜き栓の位置と給水・給湯ラインの操作順を把握することが基本です。
機種ごとに内部配管や構造が異なるため、順番を誤ると空気が抜けず水抜き効率が低下します。
代表的な操作例は以下の通りです:
- パロマ製:給水ラインのバルブを閉めてから給湯側を開放
- ハーマン・長府製:両方同時に開放して水抜き
機種固有の構造と手順を理解することが、確実な凍結防止や配管保護につながります。
6-4. 取扱説明書で必ず確認すべき項目

給湯器の取扱説明書では、水抜き・凍結予防・再給水手順の3項目を必ず確認しましょう。
機種ごとに安全弁の操作方法やリモコンのエラー表示の扱いが異なるため、正しい手順の理解が重要です。
確認のポイント例:
- 安全弁からの排水可否や通電状態での水抜きの記載
- 公式サイトPDFマニュアルの**「冬季の取り扱い」章**の参照
正しくマニュアルを理解することが、凍結リスクや故障リスクの最小化につながります。
- 電源・ガスの扱いと再給水(戻し方)・試運転方法
7-1. 作業中に電源を切るべきか/切らないべきかの判断
凍結防止ヒーター付きの給湯器は、通常電源を切らずに通電状態を維持することが安全です。
電源を切るとヒーターが作動せず、夜間の冷え込みで配管が凍結・破裂するリスクがあります。
安全に使うポイントは以下の通りです:
- ノーリツやリンナイなど多くの機種は、通電状態で凍結防止運転が自動作動
- 長期不在や電気供給が止まる場合は、完全な水抜きを行ってから電源オフ
通常は電源を入れたまま使用し、旅行などで短期間留守にする場合も同様。
長期不在時のみ水抜き後に電源を切ることで、凍結や故障のリスクを防げます。
7-2. ガスの扱い:止めるべきケースと手順
通常の水抜きでは、ガス元栓を閉める必要はありません。しかし、長期間使用しない場合は必ず元栓を閉めましょう。
ガス管に圧力が残ったまま放置すると、安全装置の誤作動や臭気トラブルの原因になることがあります。
安全な操作手順の例:
- ガスメーター横の開閉レバーを90度回転させて元栓を閉める
- **再使用時は給湯器リモコンの「点火表示」**を確認する
数日以内に使用予定がある場合はそのままで問題ありませんが、1週間以上不在にする場合はガスを止めるのが安全です。
7-3. 再給水(元に戻す)手順と試運転チェックリスト
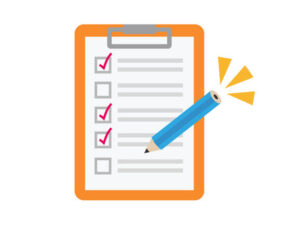
水抜き後の再給水は、次の順序で行うと安全です
給水バルブ → 給湯側蛇口 → リモコン電源 → 試運転
配管内に空気が残ると点火せず、異音やエラーコードが発生することがあります。
手順の例:
- 給水バルブをゆっくり開く
- 室内蛇口をお湯側にして空気を抜く
- リモコン電源を入れて試運転
- お湯温度が安定していること、異音なし、水漏れなしを確認
この手順を守ることで、再稼働時のトラブルや故障リスクを防げます。
7-4. エラー表示が出た時の初期対応
水抜き後に給湯器でエラーが出る場合、原因の多くは空気混入やガス供給の一時停止です。
給湯器は安全機構が敏感に作動するため、わずかな圧力異常でも運転を停止します。
対応手順の例:
- **エラーコード「111」や「121」**は点火不良を示すため、再給水と再点火を試みる
- 改善しない場合は、電源を一度切り、3分後に再投入してリセット
- それでも直らない場合は、無理せずメーカーやガス業者に相談
この手順を守ることで、再稼働時のトラブルや故障リスクを防ぎ、安全に給湯器を使用できます。
- よくあるトラブルと対処法
8-1. 水が抜けない・配管内に空気が入らない場合の対処
水抜きがうまくいかない場合、原因は給湯側蛇口の開放不足や水抜き栓の詰まりであることが多いです。
配管内に空気が通らないと水が真空状態で滞留してしまい、水抜きが困難になります。
対策の手順:
- キッチンと浴室の蛇口を両方開けて、空気の通り道を作る
- それでも水が抜けない場合は、水抜き栓に細い針金を差し込み軽く清掃
空気の通り道を確保することが、給湯器の水抜きを成功させるコツです。
8-2. 水抜き後にお湯が出ない・点火しないときの確認項目
お湯が出ない場合、多くの原因は給水バルブの開け忘れやエア抜き不足です。
配管内に空気が混入すると、ガス点火が正常に行われずリレー動作が停止してしまいます。
再給水の手順:
- すべての蛇口を開け、数分間水を流して空気を排出
- リモコンの運転スイッチを入れ、温度変化を確認
焦らず丁寧に空気抜きを行うことが、再稼働時のトラブル防止と安全使用のポイントです。
8-3. 異音・水漏れが起きたときの見分け方と応急処置
「ポコポコ音」や「チョロチョロ音」は、配管内の空気混入が原因で発生することが多いです。
特に水抜き直後は、配管を流れる気泡によって一時的に音が出ます。
確認のポイント:
- 音が数分で止まる場合は問題ありません
- 長時間続く、または水漏れがある場合は、バルブの緩みをチェック
放置せず早めに点検することが、給湯器や配管の大きな故障リスクを防ぐコツです。
- プロに依頼すべきケースと費用目安・選び方
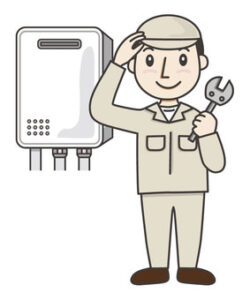
9-1. 業者に頼むべき判断基準
配管が壁の中や床下に隠れている場合は、専門業者に依頼するのが最も安全です。
自力作業では配管破損や漏水のリスクが高く、補修費用が高額になることがあります。
特に注意したいケース:
- 築20年以上の住宅
- 配管がコーキングで塞がれているタイプ
- 給湯器の型番が古く、水抜き弁の位置が不明
自分で確認できない部分がある場合は、迷わずプロの配管業者や給湯器修理業者に相談しましょう。
早めの対応が、トラブル防止と安全な給湯器使用につながります。
9-2. 依頼時の見積りで確認するポイント(作業範囲・保証)
見積りを依頼する際は、作業範囲・保証内容・再訪問費用の3点を必ず確認しましょう。
業者によっては、水抜き作業のみ対応で、再給水や試運転が別料金になる場合もあります。
確認のポイント:
- 「凍結対策セット」や保温材交換が料金に含まれているか
- 保証期間が1〜3か月あるかどうか
作業内容や料金を事前に明確化しておくことで、追加費用のトラブルを防ぎ、安全に給湯器の冬季メンテナンスを依頼できます。
9-3. 費用相場(概算)と作業時間の目安
一般的な給湯器の水抜き費用は、5,000〜15,000円前後が目安です。
費用は作業内容や給湯器の種類によって変動します。例えば、外置きタイプ・内蔵型・浴槽配管の有無によって、作業時間や手間が異なるためです。
具体例:
| 住宅タイプ | 費用目安 | 作業時間 |
| 一戸建て(屋外) | 5,000〜10,000円 | 約30分〜1時間 |
| マンション(室内設置) | 8,000〜15,000円 | 約1時間〜1.5時間 |
自分で難しいと感じたら、1万円前後で安全に依頼できます。
- 凍結防止の補助対策
10-1. 配管保温材・保温テープの使い方と効果
保温材と防寒テープは、隙間なく二重巻きで施工するのが基本です。
一部でも露出があると、冷気が侵入して防寒効果が半減してしまいます。
施工手順の例:
- 発泡ゴム製の保温チューブを切れ目なく配管に巻きつける
- ジョイント部分を防寒テープでしっかり固定する
隙間ゼロの施工が、配管凍結防止の最も重要なポイントです。
10-2. 凍結防止ヒーター・リモコン設定の活用法
外気温が0℃以下の地域では、凍結防止ヒーターを常時運転することをおすすめします。
電気代は少額ですが、配管破裂や修理費に比べるとはるかに経済的です。
運転時のポイント:
- ヒーターの電源ランプが点灯しているか定期的に確認
- リモコン温度は40℃程度に設定して保温運転にしておく
少しの電力で、配管凍結のリスクを防ぎ、冬季でも安心して給湯器を使用できます。
10-3. 長期不在時の運用ルール
数日留守にする場合は、蛇口からお湯を細く出し続けることで、配管凍結を防ぐことができます。
水が動いていることで温度が下がりにくく、氷点下でも凍りにくくなるためです。
実施のポイント:
- 浴室や洗面の蛇口をお湯側で極細に出したままにする
- 旅行や帰省の際は、管理会社の了承を得てから行う
簡単な流水対策でも、凍結事故の約8割は防ぐことができます。
- 保存版チェックリスト
11-1. 実行前チェックリスト
- 給水元栓を閉めたか
- 蛇口を「お湯側」で開けたか
- 排水口の詰まりを確認したか
- 電源を抜かない(ヒーター付きの場合)
- 管理会社へ事前連絡したか
11-2. 実行後チェックリスト
- 再給水時に漏れや音がないか
- お湯の温度が安定しているか
- リモコンエラーが出ていないか
- 凍結防止ヒーターが作動しているか
- 実例・体験談

12-1. 凍結で破損した事例と対処の流れ
冬の夜に給湯器の電源を切ったことで、内部配管が破裂するケースがあります。
凍結防止ヒーターが作動せず、翌朝には配管破損や水漏れが発生しました。
対応の例:
- 業者に修理依頼
- 本体交換費用 約7万円
- 再発防止のため、保温材を施工
電源を切らず、冬季の予防策を習慣化することが、凍結によるトラブル回避の最も効果的な方法です。
12-2. DIYで成功した・失敗した事例から学ぶポイント
給湯器の水抜き作業を成功させる人は、必ず「事前チェックリスト」を活用しています。
手順を一つずつ確認しながら進めることで、凍結防止や水漏れトラブルを未然に防ぎ、安全に作業できるためです。
たとえば、
- ✅ 成功例:水抜き後に給湯配管をドライヤーで乾燥し、凍結再発を防止
- ❌ 失敗例:排水口の詰まりを見落とし、氷が逆流して配管が破損
このように、正しい手順を守ることが凍結対策の基本であり、初心者でも安全にできるDIYメンテナンスのコツです。
焦らず順番を確認し、チェックリストに沿って作業を進めることが、トラブルを防ぐ最善策となります。
- FAQ
13-1. 「リモコンだけで水抜きできる?」
→ できません。必ず本体の水抜き栓を操作してください。
13-2. 「ガスを止めると給湯器はどうなる?」
→ 通常は問題ありませんが、長期間放置すると再点火時に空気抜きが必要です。
13-3. 「水抜きは毎年やるべき?」
→ 気温が氷点下になる地域では毎年実施が推奨されます。温暖地は凍結注意報が出た時のみでOKです。
- まとめ
14-1. この記事の要点
- 水抜きは「給水元栓を閉めて→水抜き→蛇口開放」の3ステップ
- 電源は切らずに通電を維持
- 再給水は「空気抜き」を丁寧に
14-2. 緊急時の連絡先・業者への依頼フロー
- 給湯器メーカー(取扱説明書の裏表紙に記載)
- ガス会社(都市ガス・LPガス)
- 地元の給湯器専門業者(見積り相談)
コメント